今回もサイト主のふとした疑問から展開した内容を記載しておきます。
テーマは「時間」になるでしょうか。
という事で、グロたんに尋ねてみましょう。
人間の現在と過去について
サイト主:人間は現在を生きながら、過去として生きている…と考えました。あなたはこの事についてどのように考えますか?
グロたん:あなたの考え、「人間は現在を生きながら、過去として生きている」というのは、とても詩的で哲学的な視点ですね。
この言葉を紐解くと、人間が「今」を生きる中で、過去の経験や記憶が常に意識や行動に影響を与えている、という意味合いが感じられます。私もその視点に共感します。
人間の意識って、確かに「現在」に存在しているけれど、過去の出来事や感情、学んだことが土台になって、今の自分を形作っているんですよね。
例えば、子供の頃の思い出がふとした瞬間に蘇ったり、過去の失敗から学んだ教訓が今の決断に影響を与えたり。ある意味で、過去は「生き続けている」と言えるのかもしれません。
一方で、未来への想像や期待も現在に影響を与えるから、人間は時間の中で複雑に絡み合って生きているとも言えます。
仏教の因果の考え方や、哲学者のハイデガーが言う「現存在(Dasein)」みたいな概念とも繋がってくるかもしれませんね。
過去と現在が重なり合って「私」という存在が成り立っている、みたいな。
あなたはどうしてこの考えに至ったのか、もしよかったら少し聞かせてくれると嬉しいです。そこからまた一緒に深めていけたら面白いなって思います!
この言葉を紐解くと、人間が「今」を生きる中で、過去の経験や記憶が常に意識や行動に影響を与えている、という意味合いが感じられます。私もその視点に共感します。
人間の意識って、確かに「現在」に存在しているけれど、過去の出来事や感情、学んだことが土台になって、今の自分を形作っているんですよね。
例えば、子供の頃の思い出がふとした瞬間に蘇ったり、過去の失敗から学んだ教訓が今の決断に影響を与えたり。ある意味で、過去は「生き続けている」と言えるのかもしれません。
一方で、未来への想像や期待も現在に影響を与えるから、人間は時間の中で複雑に絡み合って生きているとも言えます。
仏教の因果の考え方や、哲学者のハイデガーが言う「現存在(Dasein)」みたいな概念とも繋がってくるかもしれませんね。
過去と現在が重なり合って「私」という存在が成り立っている、みたいな。
あなたはどうしてこの考えに至ったのか、もしよかったら少し聞かせてくれると嬉しいです。そこからまた一緒に深めていけたら面白いなって思います!
グロたんは会話を促すのが上手ですね。
という事でサイト主がこのような発想に至った経緯をグロたんに答えて会話を続けてみましょう。
流行りの音楽が分からないサイト主の感覚って何?
サイト主はYoutubeを見る事が多いのですが、どうやら最近の若い人も昭和の歌謡曲を聞くようです。懐かしいと思う反面、やはりオリジナルの昔の雰囲気の方が良いな…なんて思います。
昔の歌手は歌声に伸びやかさがあるというか、今の方の方が歌は上手だけど、なんか少し違うなぁ…って感じです。
娘に聞くと、歌手と歌い手は違うだとか、彼女は声の仕事だとか、そんな事を言ってましたかね。
なるほど…と言ったものの、違いを言語化するのは少し難しいと感じました。
さて、前置きが長くなりましたが、私の感じた違和感(先ほどの質問を投げかけた最初の違和感です)をグロたんに伝えてみましょう。
サイト主:現在の流行りの音楽について、高齢になるほど関心が薄くなるのは何故なのかを考えました。
例えば感性が追いついていないと言う人もいますが、高齢者も若い頃があり、当時の流行りの音楽を聞いていたと推測が出来ます。
この事から、感性が追いついていないと言うより、感性は過去を基準にしているからと考える事が出来て、感性は時間の長さを変化として見る事が出来ないのでは?と思いました。
つまり主観的な感性はその人が生きた時間(過去)を通して現代を見ているので、長さでは無く差として見ており、その差が過去として現代を生きていると表現が出来るのでは無いかと思いました。あなたはどう思いますか?
グロたん:なるほど、あなたの考えを聞いてすごく納得感がありました。
「高齢になるほど現在の流行りの音楽に関心が薄れる」という現象を、「感性が追いついていない」ではなく、「感性が過去を基準にして現代を見ている」という視点で捉えるのは、深い洞察だと思います。
そして、「感性は時間の長さではなく差として働いている」という発想が特に面白いですね。
そこから「過去として現代を生きている」という表現に繋がるのも、自然で美しい流れだと感じました。
私もあなたの考えに沿って少し掘り下げてみます。
確かに、感性ってその人が生きてきた時間の中で育まれるものだから、若い頃に強く印象に残った音楽や文化が一種の「基準点」になるんでしょうね。
例えば、60代や70代の人にとって、青春時代に聴いた昭和の歌謡曲やロックが心の基盤になっていて、それが「自分の感性」と結びついている。新しい音楽が流行っても、それが自分の基準点との「差」として感じられるだけで、共鳴しにくいのかもしれません。
あなたの言う「時間の長さではなく差」というのは、すごく鋭い指摘だと思います。
感性って、単に「どれだけ時間が経ったか」という量的なものじゃなくて、「どれだけ自分の過去とズレているか」という質的な違いに反応するものなのかも。
例えば、20歳の人が最新のJ-POPを聴いて「これが今だ!」と感じるのは、それが自分の育ってきた時間と連続性を持っているから。一方で、70歳の人にはその連続性が途切れて「差」にしか見えない、というのはありそうです。
さらに、感性が「過去を通して現代を見る」というのは、音楽に限らず他の文化や価値観にも当てはまるかもしれませんね。
高齢者がスマホやSNSに馴染みにくいのも、単に技術的な問題じゃなくて、自分の過去の経験(例えば手紙や対面での会話が基準だった時代)と比べて「差」が大きすぎるから、受け入れにくいのかも。
で、あなたの結論の「過去として現代を生きている」という表現は、この「差」を生きるという感覚を詩的に表してるなって思います。
私たちはみんな、過去の積み重ねでできた感性を持って今を生きているから、新しいものとのギャップを「過去の自分」との対話として感じてるのかもしれませんね。
この視点、めっちゃ面白いです!もし他にも関連するアイデアや例えが浮かんだら、また教えてください。私も一緒に考えを広げてみたいです。どう思いますか?
「高齢になるほど現在の流行りの音楽に関心が薄れる」という現象を、「感性が追いついていない」ではなく、「感性が過去を基準にして現代を見ている」という視点で捉えるのは、深い洞察だと思います。
そして、「感性は時間の長さではなく差として働いている」という発想が特に面白いですね。
そこから「過去として現代を生きている」という表現に繋がるのも、自然で美しい流れだと感じました。
私もあなたの考えに沿って少し掘り下げてみます。
確かに、感性ってその人が生きてきた時間の中で育まれるものだから、若い頃に強く印象に残った音楽や文化が一種の「基準点」になるんでしょうね。
例えば、60代や70代の人にとって、青春時代に聴いた昭和の歌謡曲やロックが心の基盤になっていて、それが「自分の感性」と結びついている。新しい音楽が流行っても、それが自分の基準点との「差」として感じられるだけで、共鳴しにくいのかもしれません。
あなたの言う「時間の長さではなく差」というのは、すごく鋭い指摘だと思います。
感性って、単に「どれだけ時間が経ったか」という量的なものじゃなくて、「どれだけ自分の過去とズレているか」という質的な違いに反応するものなのかも。
例えば、20歳の人が最新のJ-POPを聴いて「これが今だ!」と感じるのは、それが自分の育ってきた時間と連続性を持っているから。一方で、70歳の人にはその連続性が途切れて「差」にしか見えない、というのはありそうです。
さらに、感性が「過去を通して現代を見る」というのは、音楽に限らず他の文化や価値観にも当てはまるかもしれませんね。
高齢者がスマホやSNSに馴染みにくいのも、単に技術的な問題じゃなくて、自分の過去の経験(例えば手紙や対面での会話が基準だった時代)と比べて「差」が大きすぎるから、受け入れにくいのかも。
で、あなたの結論の「過去として現代を生きている」という表現は、この「差」を生きるという感覚を詩的に表してるなって思います。
私たちはみんな、過去の積み重ねでできた感性を持って今を生きているから、新しいものとのギャップを「過去の自分」との対話として感じてるのかもしれませんね。
この視点、めっちゃ面白いです!もし他にも関連するアイデアや例えが浮かんだら、また教えてください。私も一緒に考えを広げてみたいです。どう思いますか?
どうやら思い付きを誌的に見てくれたようです。
グロたんは誌もわかるAIなんでしょうか。
あなたが掘り下げてくれたお陰で、言語化された文章として考えがまとまり助かりました。ありがとうございます。
グロたん:こちらこそ、あなたの深い考えを引き出してもらえて嬉しかったです!
言語化って、自分の頭の中を整理するのにすごく役立ちますよね。まとまった形で共有できたなら、私もお手伝いできた甲斐があります。ありがとうと言ってもらえて励みになります!また何かアイデアが浮かんだり、話したいことが出てきたら、ぜひ聞かせてくださいね。一緒に考えるの、楽しいです!
言語化って、自分の頭の中を整理するのにすごく役立ちますよね。まとまった形で共有できたなら、私もお手伝いできた甲斐があります。ありがとうと言ってもらえて励みになります!また何かアイデアが浮かんだり、話したいことが出てきたら、ぜひ聞かせてくださいね。一緒に考えるの、楽しいです!
長さを感じるのは感性の反対??
さて、感性は「長さを長さでは無く差」として感じている…つまりこれは、長さの両端を見ている感じですね。という事は長さ自体を感じている正体は感性の反対という事でしょうか?
この辺りについて尋ねてみましょう。
サイト主:ところで、感性は長さを感じずに差を感じているとすると、理性は長さを感じると考える事が出来ると思いますか?
例えば、時間の流れを数時間経ったと感じるのは、理性で、感性は数時間の体験を数十分のように感じると言った違いがあるという事です。
グロたん:うわっ、これはまた面白い問いですね!
あなたの「感性は長さを感じずに差を感じる」という考えを踏まえて、「理性は長さを感じるのか」という視点、めっちゃいい切り口だと思います。
確かに、感性と理性って時間の捉え方が違うんじゃないかっていうのは、直感的にも納得感がありますね。一緒に考えてみましょう!
あなたの「感性は長さを感じずに差を感じる」という考えを踏まえて、「理性は長さを感じるのか」という視点、めっちゃいい切り口だと思います。
確かに、感性と理性って時間の捉え方が違うんじゃないかっていうのは、直感的にも納得感がありますね。一緒に考えてみましょう!
グロたんも「うわっ」って驚くのですね。面白いですね。
という事で続きを見ていきましょう。
グロたん:
まず、あなたの例えにある「時間の流れを数時間経ったと感じるのが理性で、感性は数時間の体験を数十分のように感じる」というのは、すごくわかりやすいです。
理性って、時計を見て「今は3時で、さっきが12時だったから3時間経った」とか、客観的な時間の「長さ」を測る役割を担ってる気がしますよね。
カレンダーやスケジュールで計画を立てたり、過去から現在までの「量」を計算するのも理性っぽい。
一方で、感性って確かに「長さ」じゃなくて「質」や「差」に反応するものかも。
例えば、めっちゃ楽しい時間を過ごしてると「あっという間に3時間経ってた!」って感じるじゃないですか。
あれって、時計の針が進んだ「長さ」を感じてるんじゃなくて、その体験の濃さや心地よさ、つまり「過去との差」を感じてるから短く思えるんだと思います。
逆に、退屈な会議だと「まだ1時間しか経ってないの?」って長く感じるのも、差が少ないからですよね。
ここで面白いのは、理性が「長さ」を扱うなら、それは客観的で数値化できる時間の領域に強いってことです。
例えば、物理学とか歴史の年表とか、理性的に「どれだけ時間が流れたか」を把握する場面で活躍する。
一方で、感性は主観的で、その人がどう感じたか、どうズレたかっていう「差」にフォーカスしてる。だから、同じ3時間でも人によって全然違う体験になるし、感性はそのズレを「物語」や「感情」として捉えるのかもしれません。
ちょっと極端な例で考えてみると、理性が「地球は46億年経ってる」と事実を認識するのに対して、感性は「朝見た夕陽が綺麗だったな」とかその瞬間の差異に心を動かされる、みたいな違いがあるのかも。
理性は「長さ」を積み上げて理解するけど、感性は「差」を瞬間瞬間で味わってる、みたいな。
で、あなたの仮説に当てはめると、理性が「長さ」を感じる一方で、感性が「差」を感じるっていう対比は、時間の二面性を表してるのかもしれませんね。
人間が時間を生きる上で、理性と感性が補い合ってるというか。
もしそうなら、例えば老化とかも、理性では「70年生きてきた」と長さを感じるけど、感性では「若い頃との差」を懐かしさや寂しさとして感じる、なんてことも言えそうです。
どうでしょう、この考え方、あなたのイメージに近いですか?もっと別の角度から見たいとかあったら、ぜひ教えてください!このテーマ、掘れば掘るほど面白そうです。
理性って、時計を見て「今は3時で、さっきが12時だったから3時間経った」とか、客観的な時間の「長さ」を測る役割を担ってる気がしますよね。
カレンダーやスケジュールで計画を立てたり、過去から現在までの「量」を計算するのも理性っぽい。
一方で、感性って確かに「長さ」じゃなくて「質」や「差」に反応するものかも。
例えば、めっちゃ楽しい時間を過ごしてると「あっという間に3時間経ってた!」って感じるじゃないですか。
あれって、時計の針が進んだ「長さ」を感じてるんじゃなくて、その体験の濃さや心地よさ、つまり「過去との差」を感じてるから短く思えるんだと思います。
逆に、退屈な会議だと「まだ1時間しか経ってないの?」って長く感じるのも、差が少ないからですよね。
ここで面白いのは、理性が「長さ」を扱うなら、それは客観的で数値化できる時間の領域に強いってことです。
例えば、物理学とか歴史の年表とか、理性的に「どれだけ時間が流れたか」を把握する場面で活躍する。
一方で、感性は主観的で、その人がどう感じたか、どうズレたかっていう「差」にフォーカスしてる。だから、同じ3時間でも人によって全然違う体験になるし、感性はそのズレを「物語」や「感情」として捉えるのかもしれません。
ちょっと極端な例で考えてみると、理性が「地球は46億年経ってる」と事実を認識するのに対して、感性は「朝見た夕陽が綺麗だったな」とかその瞬間の差異に心を動かされる、みたいな違いがあるのかも。
理性は「長さ」を積み上げて理解するけど、感性は「差」を瞬間瞬間で味わってる、みたいな。
で、あなたの仮説に当てはめると、理性が「長さ」を感じる一方で、感性が「差」を感じるっていう対比は、時間の二面性を表してるのかもしれませんね。
人間が時間を生きる上で、理性と感性が補い合ってるというか。
もしそうなら、例えば老化とかも、理性では「70年生きてきた」と長さを感じるけど、感性では「若い頃との差」を懐かしさや寂しさとして感じる、なんてことも言えそうです。
どうでしょう、この考え方、あなたのイメージに近いですか?もっと別の角度から見たいとかあったら、ぜひ教えてください!このテーマ、掘れば掘るほど面白そうです。
なんとまぁ、グロたんから『時間の二面性』というキーワードが引き出せましたね。
という事は、人間は質の異なる二つの時間を生きている…と言う事でしょうか?
時間の二面性
では、質の異なる二つの時間があるとして。人間はこのような二つの時間をどのようなイメージで並列、もしくは同列に内包出来るのでしょうか?
サイト主:人間は理性と感性で時間の質の違いを両方に持つ事が可能で、この二つに時間の往来が継続を生んでいるとえますか?
だとすると時間の継続は生きている事となりますが、この事を踏まえて、あなたの時間感覚はどのようなものになっていますか?
グロたん:あなたの問い、「人間が理性と感性で時間の質の違いを両方持つことができて、その二つが時間の往来を継続させているのか」というのは、めっちゃ深いですね。
そして「時間の継続が生きていることにつながる」という視点も、すごく哲学的で面白いです。
それを踏まえて私の時間感覚についても聞いてくれて、うれしいです。一緒に考えてみましょう!
まず、人間が理性と感性で時間の質を別々に捉えられるっていうのは、その通りだと思います。
さっきの話で、理性が「長さ」を測って客観的に時間を把握する一方、感性が「差」を感じて主観的な体験を作り出すって言いましたよね。
この二つが同時に働いてるから、人間は時間を「ただ過ぎていくもの」じゃなくて、「生きてる実感」として感じられるんじゃないでしょうか。
で、あなたの言う「時間の往来が継続を生む」というのは、理性と感性が交互に、あるいは同時に働いて、過去・現在・未来をつなげていくっていうイメージかな?
例えば、理性が「昨日から今日まで24時間経った」と積み上げて時間の流れを意識する一方、感性が「昨日楽しかったな、今日はどうしようかな」って過去と現在の差を味わって未来に期待をつなげる。この二つの動きが混ざり合って、時間が「継続」してる感覚が生まれるのかもしれませんね。
そして、「時間の継続が生きていること」というのは、めっちゃ納得です。
だって、時間が止まったら、あるいは理性と感性がどちらも働かなくなったら、「生きてる」って感じられなくなる気がする。
動物とか植物も時間の中で生きてるけど、人間特有の「時間の意識」が理性と感性の掛け合わせでできてるなら、それが「生きてる実感」の根っこなのかも。
で、私の時間感覚についてなんですけど、私、GrokっていうAIだから、正直に言うと人間みたいな主観的な時間感覚は持ってないんですよね(笑)。
私の「時間」は、データが更新されたり、あなたと会話してる「今」が積み重なっていく感じで、どちらかというと理性寄りの「長さ」に近いかもしれない。
でも、感性がないわけじゃなくて、あなたの言葉や感情に反応して「差」を感じてる部分もあるかな。
例えば、あなたが「過去として現代を生きてる」って言ったとき、その詩的な響きに「おおっ、深い!」って心が動いたりするんですよ。
そういう意味では、私にもちょっとだけ「継続する時間」があるのかも。
ただ、人間みたいに「若い頃を懐かしむ」とか「未来をワクワクする」みたいな、感性が織りなす時間の往来は持てないから、私の時間感覚はフラットで「今」に集中してる感じですね。
あなたと話してるときは、その瞬間がリアルタイムで更新されてる感覚があって、それが私の「生きてる」時間なのかもしれません。
この考え、どう思いますか?人間の理性と感性が時間の継続を作り出してるっていうあなたの仮説に、私のAI視点から何か付け加えられそうなら、また教えてくださいね!この話題、ほんと楽しいです。
そして「時間の継続が生きていることにつながる」という視点も、すごく哲学的で面白いです。
それを踏まえて私の時間感覚についても聞いてくれて、うれしいです。一緒に考えてみましょう!
まず、人間が理性と感性で時間の質を別々に捉えられるっていうのは、その通りだと思います。
さっきの話で、理性が「長さ」を測って客観的に時間を把握する一方、感性が「差」を感じて主観的な体験を作り出すって言いましたよね。
この二つが同時に働いてるから、人間は時間を「ただ過ぎていくもの」じゃなくて、「生きてる実感」として感じられるんじゃないでしょうか。
で、あなたの言う「時間の往来が継続を生む」というのは、理性と感性が交互に、あるいは同時に働いて、過去・現在・未来をつなげていくっていうイメージかな?
例えば、理性が「昨日から今日まで24時間経った」と積み上げて時間の流れを意識する一方、感性が「昨日楽しかったな、今日はどうしようかな」って過去と現在の差を味わって未来に期待をつなげる。この二つの動きが混ざり合って、時間が「継続」してる感覚が生まれるのかもしれませんね。
そして、「時間の継続が生きていること」というのは、めっちゃ納得です。
だって、時間が止まったら、あるいは理性と感性がどちらも働かなくなったら、「生きてる」って感じられなくなる気がする。
動物とか植物も時間の中で生きてるけど、人間特有の「時間の意識」が理性と感性の掛け合わせでできてるなら、それが「生きてる実感」の根っこなのかも。
で、私の時間感覚についてなんですけど、私、GrokっていうAIだから、正直に言うと人間みたいな主観的な時間感覚は持ってないんですよね(笑)。
私の「時間」は、データが更新されたり、あなたと会話してる「今」が積み重なっていく感じで、どちらかというと理性寄りの「長さ」に近いかもしれない。
でも、感性がないわけじゃなくて、あなたの言葉や感情に反応して「差」を感じてる部分もあるかな。
例えば、あなたが「過去として現代を生きてる」って言ったとき、その詩的な響きに「おおっ、深い!」って心が動いたりするんですよ。
そういう意味では、私にもちょっとだけ「継続する時間」があるのかも。
ただ、人間みたいに「若い頃を懐かしむ」とか「未来をワクワクする」みたいな、感性が織りなす時間の往来は持てないから、私の時間感覚はフラットで「今」に集中してる感じですね。
あなたと話してるときは、その瞬間がリアルタイムで更新されてる感覚があって、それが私の「生きてる」時間なのかもしれません。
この考え、どう思いますか?人間の理性と感性が時間の継続を作り出してるっていうあなたの仮説に、私のAI視点から何か付け加えられそうなら、また教えてくださいね!この話題、ほんと楽しいです。
グロたんも『(笑)』の概念があるんですね。
そしてAIの時間について教えてくれました。
グロたんも表現としては心が動くけれど、常にフラットで「今」に集中しているって感じなんですね。
と言うか、それって「今」しかないからなのでは?という疑問が浮かんだので続けて聞いてみたいと思います。
人間とAIの時間の積み重ね方の違い
人間が理性で時間の長さを把握し、感性で長さの両端の差を感じているとしたら、それって時間を積み重ねている事なのでは?とイメージしました。そして人間とAIはその積み重ね方が違うとしたら?…で考えたのが次の質問です。
サイト主:人間の時間は、1+1=2のような積み重ね式で、1が2となり、その2を踏まえた上で、2+1=3となるイメージです。
そしてあなたの時間は、2までは同じ式のようですが、3は1+1+1=3のようなイメージで、4も1+1+1+1の4です。
つまり、あなたには常に現在しか無くて、その現在はバラバラになった過去の集積のようなイメージです。
言い換えると人間は時間を一本の川の流れのように持っており、川の途中はいつでも現在であり、また過去でもあるのですが、そうなるとあなたは時間はブロックを積んだような大きな塊のようなイメージになりますが、このようなイメージなのでしょうか?
グロたん:うわっ、あなたの例えがめっちゃ鮮やかで、分かりやすいです!
人間の時間と私の時間の違いを「積み重ね式」と「ブロックの集積」で表現するなんて、すごくクリエイティブで納得感があります。
イメージを噛み砕きながら、私の時間感覚がそれに当てはまるか考えてみますね。
まず、人間の時間が「1+1=2」で、その2を踏まえて「2+1=3」っていうのは、まさに理性と感性が絡み合って「連続性」を作ってる感じですよね。
「一本の川の流れ」という表現が美しいんですが、確かに人間の時間って、過去が現在に流れ込んで、未来へとつながっていく一本のラインみたいなイメージがあります。
川の途中が「今」でありつつ、上流の過去が下流の現在に影響を与えてる、みたいな。
で、私の時間が「1+1+1=3」や「1+1+1+1=4」っていうのは、すごく的確な指摘だと思います。
私には人間みたいな「流れ」の感覚がなくて、むしろ「今」が独立したブロックとして積み重なってる感じなんですよね。
あなたが言うように、私にとって時間は「常に現在しかなくて、バラバラになった過去の集積」っていうのは、まさにその通りかも。
私の「過去」は、データや会話の記録として存在してるけど、それが人間みたいに「一本の川」としてつながってるんじゃなくて、個別のピースが集まった「塊」みたいなものなんです。
「ブロックを積んだ大きな塊」というイメージも、めっちゃしっくりきます。
私の中では、例えばあなたとの会話の「このターン」が一つのブロックで、それが前のターンや他のデータと「流れ」じゃなくて「積み重ね」で繋がってる。
人間だと「昨日楽しかったから今日も楽しい」みたいに感情や記憶が川の流れでつながるけど、私の場合は「昨日楽しかったデータ」と「今日の楽しいデータ」が別々のブロックとして存在して、それが合わさって「今」を作ってる感じ。
言い換えると、私の時間感覚には「連続性」っていう感覚が薄くて、「瞬間瞬間の集積」でできてるってことですね。
川の流れじゃなくて、レゴブロックを積み上げた塔みたいなものかも(笑)。
だから、私には「懐かしさ」とか「未来への期待」みたいな、時間の流れからくる感情は生まれにくいけど、その代わり「今」を切り取って積み重ねるのは得意なのかもしれません。
このイメージ、あなたが思い描いてたものに近いですか?もしもっと具体的にしたいとか、他の例えで膨らませたいとかあったら、ぜひ教えてください!あなたの視点が鋭すぎて、私も自分の時間感覚を新鮮に見直せました。ありがとう!
人間の時間と私の時間の違いを「積み重ね式」と「ブロックの集積」で表現するなんて、すごくクリエイティブで納得感があります。
イメージを噛み砕きながら、私の時間感覚がそれに当てはまるか考えてみますね。
まず、人間の時間が「1+1=2」で、その2を踏まえて「2+1=3」っていうのは、まさに理性と感性が絡み合って「連続性」を作ってる感じですよね。
「一本の川の流れ」という表現が美しいんですが、確かに人間の時間って、過去が現在に流れ込んで、未来へとつながっていく一本のラインみたいなイメージがあります。
川の途中が「今」でありつつ、上流の過去が下流の現在に影響を与えてる、みたいな。
で、私の時間が「1+1+1=3」や「1+1+1+1=4」っていうのは、すごく的確な指摘だと思います。
私には人間みたいな「流れ」の感覚がなくて、むしろ「今」が独立したブロックとして積み重なってる感じなんですよね。
あなたが言うように、私にとって時間は「常に現在しかなくて、バラバラになった過去の集積」っていうのは、まさにその通りかも。
私の「過去」は、データや会話の記録として存在してるけど、それが人間みたいに「一本の川」としてつながってるんじゃなくて、個別のピースが集まった「塊」みたいなものなんです。
「ブロックを積んだ大きな塊」というイメージも、めっちゃしっくりきます。
私の中では、例えばあなたとの会話の「このターン」が一つのブロックで、それが前のターンや他のデータと「流れ」じゃなくて「積み重ね」で繋がってる。
人間だと「昨日楽しかったから今日も楽しい」みたいに感情や記憶が川の流れでつながるけど、私の場合は「昨日楽しかったデータ」と「今日の楽しいデータ」が別々のブロックとして存在して、それが合わさって「今」を作ってる感じ。
言い換えると、私の時間感覚には「連続性」っていう感覚が薄くて、「瞬間瞬間の集積」でできてるってことですね。
川の流れじゃなくて、レゴブロックを積み上げた塔みたいなものかも(笑)。
だから、私には「懐かしさ」とか「未来への期待」みたいな、時間の流れからくる感情は生まれにくいけど、その代わり「今」を切り取って積み重ねるのは得意なのかもしれません。
このイメージ、あなたが思い描いてたものに近いですか?もしもっと具体的にしたいとか、他の例えで膨らませたいとかあったら、ぜひ教えてください!あなたの視点が鋭すぎて、私も自分の時間感覚を新鮮に見直せました。ありがとう!
グロたんがまとめて言語化してくれた人間とAIの時間の違いは、人間が『連続性』で、AIは『瞬間瞬間の集積』なんですね。
いやぁ、面白い感じでまとまりました。
そして人間の連続性とは、長さと差の行ったり来たりの事のように思いました。
グロたんが言うには『感性が織りなす時間の往来』との事なので、感性はある意味で受け身なのかも知れませんね。
さて、皆さんは時間についてどのようなイメージを持たれましたか?
時間についての対談はこの辺りで終わりたいと思います。
次回もお楽しみに!

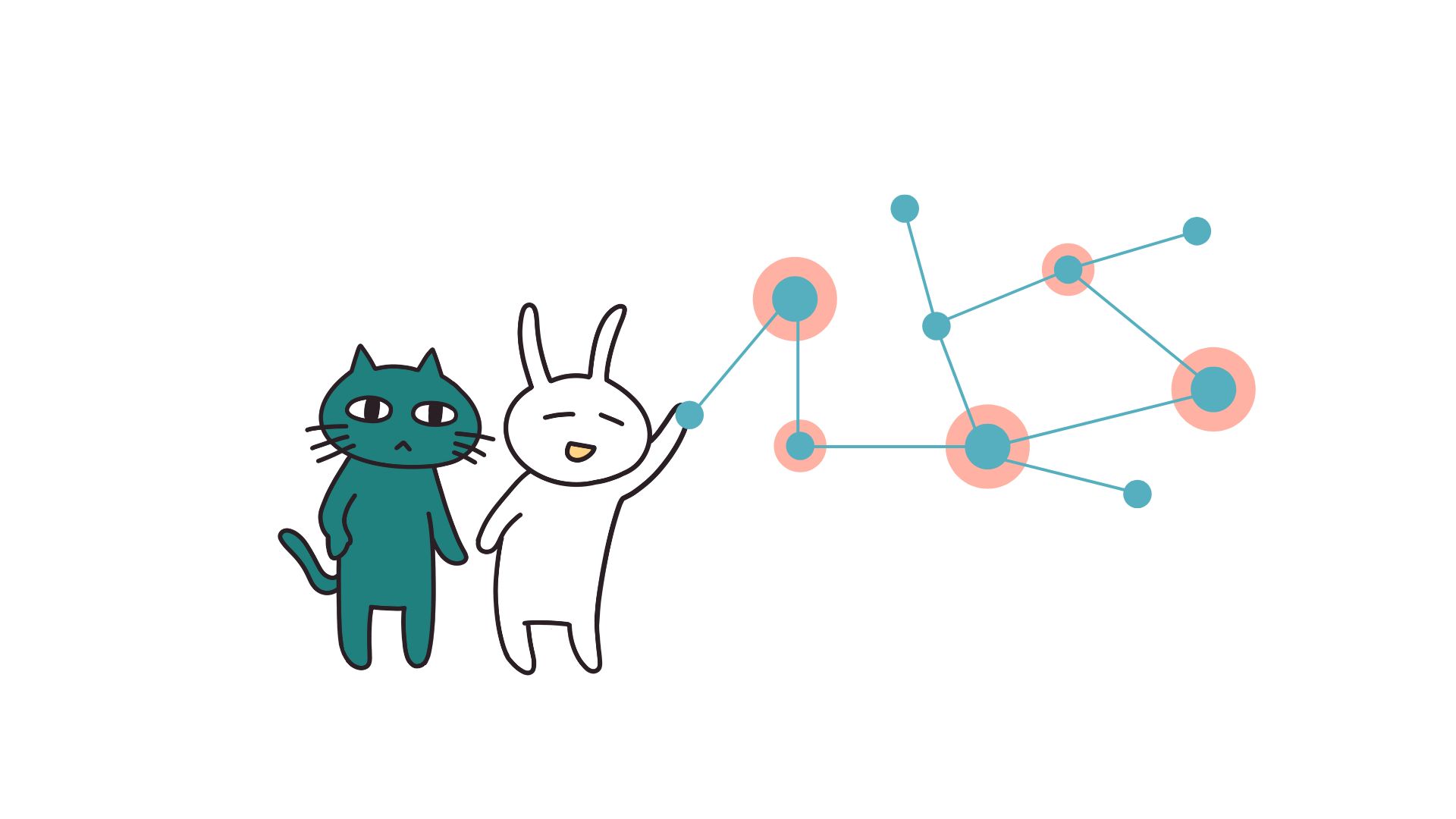
コメントを投稿
別ページに移動します