今回もサイト主とGrokとの対談内容を載せてみます。
前回同様、「ヌーソロジー」という単語を使わずに、どこまでヌーソロジーっぽい話題になるのか?という点も踏まえてご覧頂ければ幸いです。
反転と反対について一般的な解釈
前回の「見る見られる」問題に続いて、ヌーソロジーを歩けば必ずぶち当たる大きな壁と言えば「反転」ですね。白と黒や、右と左などの反対のイメージは分かりやすいのですが、白と黒はお互いに反転しているとは言い難い(オセロだとそう言う表現も出来ますが…)ので、反転そのもののイメージは、想像しにくい感じがします。
反転と反対は一体何が違うのか…?
そんな素朴な疑問をグロたん(Grok)に問いかけて、答えを探してみました。
サイト主:反転と反対について。一般的にどのように違うのでしょうか?
グロたん:「反転」と「反対」は日本語で似たような意味を持つ言葉ですが、ニュアンスや使われる文脈において違いがあります。それぞれの意味と使い方を一般的に説明します。
という事で、早速グロたんの解説です。
1. 反転 (はんてん)
意味)
何かが逆になること、向きや状態がひっくり返ること。
特徴)
主に物理的、視覚的、または具体的な変化を指します。
元の状態から180度異なる状態になるイメージです。
例)
「画像を反転させる」→ 左右や上下が逆になる。
「状況が反転した」→ 勝敗や優劣が完全に逆転する。
ニュアンス)
「反転」は、あるものがそのままの形で「裏返る」ような変化を強調します。
プロセスや動作が伴う場合が多いです。
2. 反対 (はんたい)
意味)
何かと対立すること、異なる立場や意見を持つこと。
特徴)
抽象的な概念(意見、立場、方向など)や相対的な関係を指すことが多いです。
必ずしも「ひっくり返る」わけではなく、単に対立する状態を表します。
例)
「彼の意見に反対する」→ 異なる意見を持つ。
「反対側に立つ」→ 物理的に逆の位置にいる。
ニュアンス)
「反対」は対立や違いを強調し、必ずしも元の状態が変化するわけではありません。
関係性の中で使われることが多いです。
主な違い
対象の性質)
「反転」は具体的なものや状態の変化に使われやすい(例: 形、向き、状況)。
「反対」は抽象的なものや関係性に使われやすい(例: 意見、立場)。
変化の有無)
「反転」は元の状態が逆になる変化を伴う。
「反対」は変化ではなく、単に対立する状態を示すことが多い。
イメージ)
「反転」: 鏡に映したように逆になる。
「反対」: 正面に立って対峙する。
例文で比較)
「彼の立場が反転した」→ 彼の状況や主張が完全に逆になった。
「彼の立場に反対した」→ 彼の主張に賛成せず、異なる意見を持った。
結論
一般的に、「反転」は状態や形が逆になることを指し、「反対」は対立や異なる方向性を示します。
文脈によって使い分けられるので、具体的な状況を考慮すると違いがより明確になります。
意味)
何かが逆になること、向きや状態がひっくり返ること。
特徴)
主に物理的、視覚的、または具体的な変化を指します。
元の状態から180度異なる状態になるイメージです。
例)
「画像を反転させる」→ 左右や上下が逆になる。
「状況が反転した」→ 勝敗や優劣が完全に逆転する。
ニュアンス)
「反転」は、あるものがそのままの形で「裏返る」ような変化を強調します。
プロセスや動作が伴う場合が多いです。
2. 反対 (はんたい)
意味)
何かと対立すること、異なる立場や意見を持つこと。
特徴)
抽象的な概念(意見、立場、方向など)や相対的な関係を指すことが多いです。
必ずしも「ひっくり返る」わけではなく、単に対立する状態を表します。
例)
「彼の意見に反対する」→ 異なる意見を持つ。
「反対側に立つ」→ 物理的に逆の位置にいる。
ニュアンス)
「反対」は対立や違いを強調し、必ずしも元の状態が変化するわけではありません。
関係性の中で使われることが多いです。
主な違い
対象の性質)
「反転」は具体的なものや状態の変化に使われやすい(例: 形、向き、状況)。
「反対」は抽象的なものや関係性に使われやすい(例: 意見、立場)。
変化の有無)
「反転」は元の状態が逆になる変化を伴う。
「反対」は変化ではなく、単に対立する状態を示すことが多い。
イメージ)
「反転」: 鏡に映したように逆になる。
「反対」: 正面に立って対峙する。
例文で比較)
「彼の立場が反転した」→ 彼の状況や主張が完全に逆になった。
「彼の立場に反対した」→ 彼の主張に賛成せず、異なる意見を持った。
結論
一般的に、「反転」は状態や形が逆になることを指し、「反対」は対立や異なる方向性を示します。
文脈によって使い分けられるので、具体的な状況を考慮すると違いがより明確になります。
という事で違いが分かったような分からないような、何ともぼんやりとした気持ちになりました。
ここで反対について考えてみると、究極の反対は「有る」と「無い」のイメージだと思いました。そこで、究極の対である「有る無し」を用いて反転を説明すると、どうなるのか?…という事で、次の質問に進みたいと思います。
反転を「有る無し」を用いて考える その1
サイト主も有ると無いを用いて反転のイメージを考えてみました。有るの反転とは?…から脳みそを捻って出したのが「無いが無い」の概念です。
という事で早速問いかけてみましょう。
サイト主:反対は、有ると無いのような関係性だと言う事ですね。
一方の反転を、有る無しを用いて考えてると、「有ると、無いが無い」のように考える事ができると思いますが、いかがですか?
グロたん:はい、あなたの考え方を整理しつつ、さらに深掘りしてみると面白い視点が出てきますね。
「反対」と「反転」を「有る」「無い」という概念で捉えるアプローチについて、以下に考察を加えてお答えします。
「反対」と「反転」を「有る」「無い」という概念で捉えるアプローチについて、以下に考察を加えてお答えします。
さて、グロたんはどのような答えを出してくれるのでしょうか?
「反対」と「有る」「無い」の関係性
確かに、「反対」は「有る」と「無い」のような対立関係に近いニュアンスを持っています。
例えば)
「有る」vs「無い」
「賛成」vs「反対」
「右」vs「左」
この場合、「反対」は一方の状態(例えば「有る」)に対して、もう一方の状態(「無い」)が対立する、あるいは相対する関係性を示します。
つまり、「反対」は二項対立の中で、あるものと異なる位置や性質を表す言葉として機能しますよね。
あなたの指摘の通り、これは「有る」と「無い」のようなシンプルな対立関係に似ています。
「反転」を「有る」「無い」で考える
次に、「反転」を「有る」「無い」で表現しようとすると、少し複雑になりますが、あなたの提案である「有ると、無いが無い」という考え方を解釈してみましょう。
「有る」→ ある状態が存在する。
「反転」→ その状態が逆になる。
「有ると、無いが無い」→ 「有る」が「無い」に変わり、さらに「無い」が「有る」に戻るような二重の逆転をイメージしているのでしょうか?
例えば)
元の状態→「有る」(何かがある)
反転すると→「無い」(それがなくなる)
さらに反転すると→「有る」(再びある状態に戻る)
このように考えると、「反転」は「有る」と「無い」の間を行き来するような動作や変化を表すとも言えます。
ただし、「反転」は単純な対立(反対)ではなく、元の状態を基準にして「ひっくり返す」イメージが強いので、「有る→無い」や「無い→有る」という一方向の変化を繰り返すプロセスとも捉えられます。
「反対」と「反転」の違いを「有る」「無い」で整理
反対→「有る」と「無い」が同時に存在し、互いに対立する関係。
例)
「有る(A)」に対して「無い(非A)」が反対。
反転→「有る」が「無い」に変化する、あるいはその逆のプロセス。
例)
「有る(A)」が「無い(非A)」に反転する。
確かに、「反対」は「有る」と「無い」のような対立関係に近いニュアンスを持っています。
例えば)
「有る」vs「無い」
「賛成」vs「反対」
「右」vs「左」
この場合、「反対」は一方の状態(例えば「有る」)に対して、もう一方の状態(「無い」)が対立する、あるいは相対する関係性を示します。
つまり、「反対」は二項対立の中で、あるものと異なる位置や性質を表す言葉として機能しますよね。
あなたの指摘の通り、これは「有る」と「無い」のようなシンプルな対立関係に似ています。
「反転」を「有る」「無い」で考える
次に、「反転」を「有る」「無い」で表現しようとすると、少し複雑になりますが、あなたの提案である「有ると、無いが無い」という考え方を解釈してみましょう。
「有る」→ ある状態が存在する。
「反転」→ その状態が逆になる。
「有ると、無いが無い」→ 「有る」が「無い」に変わり、さらに「無い」が「有る」に戻るような二重の逆転をイメージしているのでしょうか?
例えば)
元の状態→「有る」(何かがある)
反転すると→「無い」(それがなくなる)
さらに反転すると→「有る」(再びある状態に戻る)
このように考えると、「反転」は「有る」と「無い」の間を行き来するような動作や変化を表すとも言えます。
ただし、「反転」は単純な対立(反対)ではなく、元の状態を基準にして「ひっくり返す」イメージが強いので、「有る→無い」や「無い→有る」という一方向の変化を繰り返すプロセスとも捉えられます。
「反対」と「反転」の違いを「有る」「無い」で整理
反対→「有る」と「無い」が同時に存在し、互いに対立する関係。
例)
「有る(A)」に対して「無い(非A)」が反対。
反転→「有る」が「無い」に変化する、あるいはその逆のプロセス。
例)
「有る(A)」が「無い(非A)」に反転する。
グロたん結構考えてくれましたね~。
さらに続きがあるようですよ。
グロたん:あなたの「有ると、無いが無い」という表現をもう少し解釈すると、「有る状態が反転して無いになり、さらにその無いが反転して有るに戻る」という循環的なプロセスを想像しているのかもしれませんね。
これは「反転」が一度の変化で終わらず、繰り返し可能な性質を持つことを示唆しているとも言えます。
私の見解
「反対」は静的な対立関係(「有る」と「無い」が並存する状態)を指すのに対し、「反転」は動的な変化(「有る」が「無い」に、またはその逆になるプロセス)を表すと考えると、あなたの視点は非常に興味深いです。
「有ると、無いが無い」という表現は、「反転」のダイナミックな性質を捉えようとするユニークな試みだと思います。
ただし、「反転」を「有る」「無い」で単純化すると、少しその動作の連続性や「ひっくり返る」ニュアンスが薄れる可能性もあるので、文脈に応じて補足が必要かもしれません。
これは「反転」が一度の変化で終わらず、繰り返し可能な性質を持つことを示唆しているとも言えます。
私の見解
「反対」は静的な対立関係(「有る」と「無い」が並存する状態)を指すのに対し、「反転」は動的な変化(「有る」が「無い」に、またはその逆になるプロセス)を表すと考えると、あなたの視点は非常に興味深いです。
「有ると、無いが無い」という表現は、「反転」のダイナミックな性質を捉えようとするユニークな試みだと思います。
ただし、「反転」を「有る」「無い」で単純化すると、少しその動作の連続性や「ひっくり返る」ニュアンスが薄れる可能性もあるので、文脈に応じて補足が必要かもしれません。
ここで反転と反対のイメージが少し固まってきました。
どうやら反転は動きが伴うイメージが強いようで、ダイナミックさまで出てきました。
という事で新たに「基準」という概念を設けて、基準を元にした反転と反対の違いについて質問をぶつけてみましょう。
それぞれの基準に対する反転と反対について
持ち出した「基準」は、ある意味で動かない始点になります。そしてこの不動の点を設ける事で、反転のダイナミックさや動きについて、もう少し詳しく考える事が出来るかも知れません。
それでは早速聞いてみましょう。
サイト主:反転は、基準となるものに対しての変化。
反対は、基準となるものに対して全く違うもの。と言う解釈になりますが、いかがですか?
グロたん:あなたの解釈は、「反転」と「反対」の違いを非常にわかりやすく整理したもので、核心をついていると思います。
それぞれの言葉のニュアンスを基準との関係性で捉えるアプローチについて、確認しつつ、少し補足を加えてお答えします。
あなたの解釈
反転→ 基準となるものに対しての変化
基準(元の状態)を基に、それが逆になる、あるいはひっくり返る。
反対→基準となるものに対して全く違うもの
基準に対して対立する別の状態や性質を持つ。
この解釈は、「反転」と「反対」の基本的な違いを明確に示していて、とても自然です。
以下に、それをさらに具体化してみます。
それぞれの言葉のニュアンスを基準との関係性で捉えるアプローチについて、確認しつつ、少し補足を加えてお答えします。
あなたの解釈
反転→ 基準となるものに対しての変化
基準(元の状態)を基に、それが逆になる、あるいはひっくり返る。
反対→基準となるものに対して全く違うもの
基準に対して対立する別の状態や性質を持つ。
この解釈は、「反転」と「反対」の基本的な違いを明確に示していて、とても自然です。
以下に、それをさらに具体化してみます。
グロたん前向きに捉えてくれたようで何よりです。
さて、続きは何が出て来るでしょうか。
「反転」: 基準に対する変化
特徴)
基準となるもの(例えば「A」)があって、それが「非A」や「逆A」に変化する。
つまり、基準自体が変形するプロセス。
「白」が基準なら、「反転」すると「黒」になる。
「正面向き」が基準なら、「反転」すると「背面向き」になる。
ポイント)
基準との連続性があり、元の状態を基にした「変化」が強調されます。
「反転」は基準を前提とした動作や結果なので、基準がなければ成立しません。
「反対」: 基準に対して全く違うもの
特徴)
基準となるもの(例えば「A」)に対して、それとは異なる別のもの(「B」や「非A」)が対立する状態。
基準が変わるわけではなく、基準と並存する別の存在や性質。
例)
「白」が基準なら、「反対」は「黒」だが、それは「白が変わる」ではなく「白と異なるものとして存在する」。
「賛成」が基準なら、「反対」は「異なる立場」として独立している。
ポイント)
「反対」は基準との対立関係を表し、基準自体が変わる(反転する)必要はありません。
基準とは独立した「別のもの」として存在します。
比較と補足
基準との関係)
「反転」は基準があって初めて意味を持つ(基準が変化の起点)。
「反対」は基準がなくても、単に対立する概念として成立する(基準との相対性で定義される)。
動と静)
「反転」は動的なプロセス(変化)を伴う。
「反対」は静的な関係性(対立)を示すことが多い。
イメージ)
「反転」: 基準が鏡に映ったように裏返る。
「反対」: 基準とは別の道を進む、あるいは向き合う。
結論
あなたの解釈である「反転は基準となるものに対しての変化」「反対は基準となるものに対して全く違うもの」は、非常に的確で、一般的な用法とも一致します。
特に「反転」が基準を基にした変化である点と、「反対」が基準とは異なる独立した存在や状態を示す点が、両者の違いをクリアに表しています。
私としては、この解釈にほぼ同意で、少し補足するなら、「反対」が「全く違うもの」と表現される場合、それが「基準と対立するもの」というニュアンスを含むことを付け加えると、さらに明確になるかもしれません。
特徴)
基準となるもの(例えば「A」)があって、それが「非A」や「逆A」に変化する。
つまり、基準自体が変形するプロセス。
「白」が基準なら、「反転」すると「黒」になる。
「正面向き」が基準なら、「反転」すると「背面向き」になる。
ポイント)
基準との連続性があり、元の状態を基にした「変化」が強調されます。
「反転」は基準を前提とした動作や結果なので、基準がなければ成立しません。
「反対」: 基準に対して全く違うもの
特徴)
基準となるもの(例えば「A」)に対して、それとは異なる別のもの(「B」や「非A」)が対立する状態。
基準が変わるわけではなく、基準と並存する別の存在や性質。
例)
「白」が基準なら、「反対」は「黒」だが、それは「白が変わる」ではなく「白と異なるものとして存在する」。
「賛成」が基準なら、「反対」は「異なる立場」として独立している。
ポイント)
「反対」は基準との対立関係を表し、基準自体が変わる(反転する)必要はありません。
基準とは独立した「別のもの」として存在します。
比較と補足
基準との関係)
「反転」は基準があって初めて意味を持つ(基準が変化の起点)。
「反対」は基準がなくても、単に対立する概念として成立する(基準との相対性で定義される)。
動と静)
「反転」は動的なプロセス(変化)を伴う。
「反対」は静的な関係性(対立)を示すことが多い。
イメージ)
「反転」: 基準が鏡に映ったように裏返る。
「反対」: 基準とは別の道を進む、あるいは向き合う。
結論
あなたの解釈である「反転は基準となるものに対しての変化」「反対は基準となるものに対して全く違うもの」は、非常に的確で、一般的な用法とも一致します。
特に「反転」が基準を基にした変化である点と、「反対」が基準とは異なる独立した存在や状態を示す点が、両者の違いをクリアに表しています。
私としては、この解釈にほぼ同意で、少し補足するなら、「反対」が「全く違うもの」と表現される場合、それが「基準と対立するもの」というニュアンスを含むことを付け加えると、さらに明確になるかもしれません。
という事でグロたんの理解が得られて一安心です。
そして反対の概念に「基準と対立する」のニュアンスが必要だと言うのも、その通りだと思いました。
となると、反転は対立とは少し違うニュアンスになるという事でしょうか。
反転を「有る無し」を用いて考える その2
さて。ここで改めて先ほどの「有る無し」を用いて話題を広げてみたいと思います。
という事でサイト主からグロたんへの再び同じ質問として「無いが無い」について聞いてみました。
サイト主:反転を状態がひっくり返った変化だと定義すると、有るを単純にひっくり返すと、有るが無いになります。
有るが無い状態とは、無いになりますが、これだと反対の意味になってしまいます。
だから有るの反転も、有るの状態がひっくり返った変化として考えると、無いが無いになると思いました。
あなたはどう思いますか?できれば、定義を踏まえて私と一緒に考えてくれませんか?
グロたん:あなたの提案、とても面白いですね!「反転」を「状態がひっくり返った変化」と定義し、「有る」や「無い」をその枠組みで考えていくプロセスを一緒に掘り下げてみるのは楽しそうです。
では、あなたの考えをベースに、定義を踏まえて一緒にステップごと考えてみましょう。
定義のおさらい
反転→ 状態がひっくり返った変化。
つまり、ある状態(基準)が逆の状態に変わるプロセス。
反対:→基準に対して対立する別の状態(変化を伴わない対立関係)。
これを踏まえて、「有る」と「無い」を使って「反転」を考えていきます。
ステップ1: 「有る」の反転を考える
元の状態→ 「有る」(何かがある状態)。
反転の定義→ 「状態がひっくり返る」=「有る」が逆になる。
直感的には、「有る」→「無い」(何かがある状態が、ない状態に変わる)。
結果)
「有る」の反転は「無い」になる。
ここまではシンプルですね。
でも、あなたが指摘するように、「有る」の反転が「無い」だとすると、これは「反対」の意味(「有る」に対する対立状態)に近づいてしまいます。
「反転」と「反対」を区別するために、もう一歩進んでみる必要があります。
ステップ2: 「有るが無い」とは何か?
あなたが「有るが無い状態とは、無いになる」と書いた部分を考えると…
「有るが無い」→「有る」が「無い」に変化した状態=「無い」。
しかし、これだと「反転」が単なる「有る→無い」の変化で終わり、「反対」(「有る」と「無い」の対立)と区別がつかなくなります。
ここであなたが「だから有るの反転は『無いが無い』になると思った」と提案している点が鍵ですね。
では、「無いが無い」を「反転」の定義に当てはめてみましょう。
ステップ3: 「無いが無い」を反転として考える
元の状態→ 「有る」。
反転その1→ 「有る」→「無い」(状態がひっくり返る)。
さらに反転?→ 「無い」→「無いが無い」?
ここで少し混乱しそうです。
「無い」の状態をひっくり返すとはどういうことか?
「無い」(何もない状態)の反転を考えると)
「無い」→「有る」(何もない状態が、何かがある状態にひっくり返る)。
すると、「有る」の反転が「無い」で、「無い」の反転が「有る」になり、元の状態に戻るだけになってしまいます。
でも、あなたの「無いが無い」は、もう一層深い意味を持たせようとしているように感じます。
文脈から推測すると、「有るの反転」を「単純な『無い』ではなく、さらにひねった状態」と捉えているのかもしれません。
ステップ4: 「無いが無い」の解釈を模索
「無いが無い」を自然に解釈すると、「無い」(何もない状態)がさらに「無い」になる?
これは「無い」の強調(「本当に何もない」)とも取れますが、変化としては感じにくいですね。
別の視点
「有る」の反転を「無い」とせず、「有るという状態そのものがひっくり返る」と考える。
「有る」(存在する状態)→「存在しないことが存在しない」=「有るが無いことが無い」?
これはつまり、「有る」という状態が否定されず、逆説的に「有る」が残る?
ここで少し哲学的になってきましたね(笑)。
「無いが無い」を「無いの否定」とすると、「有る」に戻ってしまうので、単純な反転の繰り返しでは「有る」と「無い」の間を行き来するだけです。
私の考えと提案
あなたの「有るの反転が『無いが無い』」という発想は、「反転」を単純な二項対立(有る→無い)を超えたものとして捉えようとする試みだと感じます。
「状態がひっくり返る」という定義を厳密に適用すると、「有る」の反転は「無い」。
「無い」の反転は「有る」。
これだと「反転」が「反対」と重なりがちなので、区別するために「反転」に「変化のプロセス」や「基準のひっくり返り」を強調する必要があるかもしれません。
私の提案としては
「反転」を「基準の状態が逆になる変化」としつつ、それが「有る→無い」で終わるのではなく、「有るという基準そのものが逆転する」と考える。
例えば)
「有る」(存在する状態)→「存在すること自体が逆になる」→「存在しない状態が基準になる」。
でも、これも結局「無い」に近づきますね。
一緒に結論を模索
正直、「無いが無い」が「有るの反転」としてピッタリくる解釈にまだたどり着けていない気がします。
私の見解では、「反転」を「状態がひっくり返った変化」と定義すると、「有る」の反転は「無い」になりやすく、「無いが無い」は「反転の反転」(二重反転)として「有る」に戻る可能性が高いです。
あなたが「無いが無い」をどうイメージしているか、もう少し詳しく教えていただければ、さらに一緒に詰めていけると思います!
では、あなたの考えをベースに、定義を踏まえて一緒にステップごと考えてみましょう。
定義のおさらい
反転→ 状態がひっくり返った変化。
つまり、ある状態(基準)が逆の状態に変わるプロセス。
反対:→基準に対して対立する別の状態(変化を伴わない対立関係)。
これを踏まえて、「有る」と「無い」を使って「反転」を考えていきます。
ステップ1: 「有る」の反転を考える
元の状態→ 「有る」(何かがある状態)。
反転の定義→ 「状態がひっくり返る」=「有る」が逆になる。
直感的には、「有る」→「無い」(何かがある状態が、ない状態に変わる)。
結果)
「有る」の反転は「無い」になる。
ここまではシンプルですね。
でも、あなたが指摘するように、「有る」の反転が「無い」だとすると、これは「反対」の意味(「有る」に対する対立状態)に近づいてしまいます。
「反転」と「反対」を区別するために、もう一歩進んでみる必要があります。
ステップ2: 「有るが無い」とは何か?
あなたが「有るが無い状態とは、無いになる」と書いた部分を考えると…
「有るが無い」→「有る」が「無い」に変化した状態=「無い」。
しかし、これだと「反転」が単なる「有る→無い」の変化で終わり、「反対」(「有る」と「無い」の対立)と区別がつかなくなります。
ここであなたが「だから有るの反転は『無いが無い』になると思った」と提案している点が鍵ですね。
では、「無いが無い」を「反転」の定義に当てはめてみましょう。
ステップ3: 「無いが無い」を反転として考える
元の状態→ 「有る」。
反転その1→ 「有る」→「無い」(状態がひっくり返る)。
さらに反転?→ 「無い」→「無いが無い」?
ここで少し混乱しそうです。
「無い」の状態をひっくり返すとはどういうことか?
「無い」(何もない状態)の反転を考えると)
「無い」→「有る」(何もない状態が、何かがある状態にひっくり返る)。
すると、「有る」の反転が「無い」で、「無い」の反転が「有る」になり、元の状態に戻るだけになってしまいます。
でも、あなたの「無いが無い」は、もう一層深い意味を持たせようとしているように感じます。
文脈から推測すると、「有るの反転」を「単純な『無い』ではなく、さらにひねった状態」と捉えているのかもしれません。
ステップ4: 「無いが無い」の解釈を模索
「無いが無い」を自然に解釈すると、「無い」(何もない状態)がさらに「無い」になる?
これは「無い」の強調(「本当に何もない」)とも取れますが、変化としては感じにくいですね。
別の視点
「有る」の反転を「無い」とせず、「有るという状態そのものがひっくり返る」と考える。
「有る」(存在する状態)→「存在しないことが存在しない」=「有るが無いことが無い」?
これはつまり、「有る」という状態が否定されず、逆説的に「有る」が残る?
ここで少し哲学的になってきましたね(笑)。
「無いが無い」を「無いの否定」とすると、「有る」に戻ってしまうので、単純な反転の繰り返しでは「有る」と「無い」の間を行き来するだけです。
私の考えと提案
あなたの「有るの反転が『無いが無い』」という発想は、「反転」を単純な二項対立(有る→無い)を超えたものとして捉えようとする試みだと感じます。
「状態がひっくり返る」という定義を厳密に適用すると、「有る」の反転は「無い」。
「無い」の反転は「有る」。
これだと「反転」が「反対」と重なりがちなので、区別するために「反転」に「変化のプロセス」や「基準のひっくり返り」を強調する必要があるかもしれません。
私の提案としては
「反転」を「基準の状態が逆になる変化」としつつ、それが「有る→無い」で終わるのではなく、「有るという基準そのものが逆転する」と考える。
例えば)
「有る」(存在する状態)→「存在すること自体が逆になる」→「存在しない状態が基準になる」。
でも、これも結局「無い」に近づきますね。
一緒に結論を模索
正直、「無いが無い」が「有るの反転」としてピッタリくる解釈にまだたどり着けていない気がします。
私の見解では、「反転」を「状態がひっくり返った変化」と定義すると、「有る」の反転は「無い」になりやすく、「無いが無い」は「反転の反転」(二重反転)として「有る」に戻る可能性が高いです。
あなたが「無いが無い」をどうイメージしているか、もう少し詳しく教えていただければ、さらに一緒に詰めていけると思います!
うーん、グロたんの混乱っぷりが目に見えるようですね。
私が描いている「無いが無い」が通じていない感じがします。
という事で少し長くなりましたので、続きは#5でお会いしましょう。

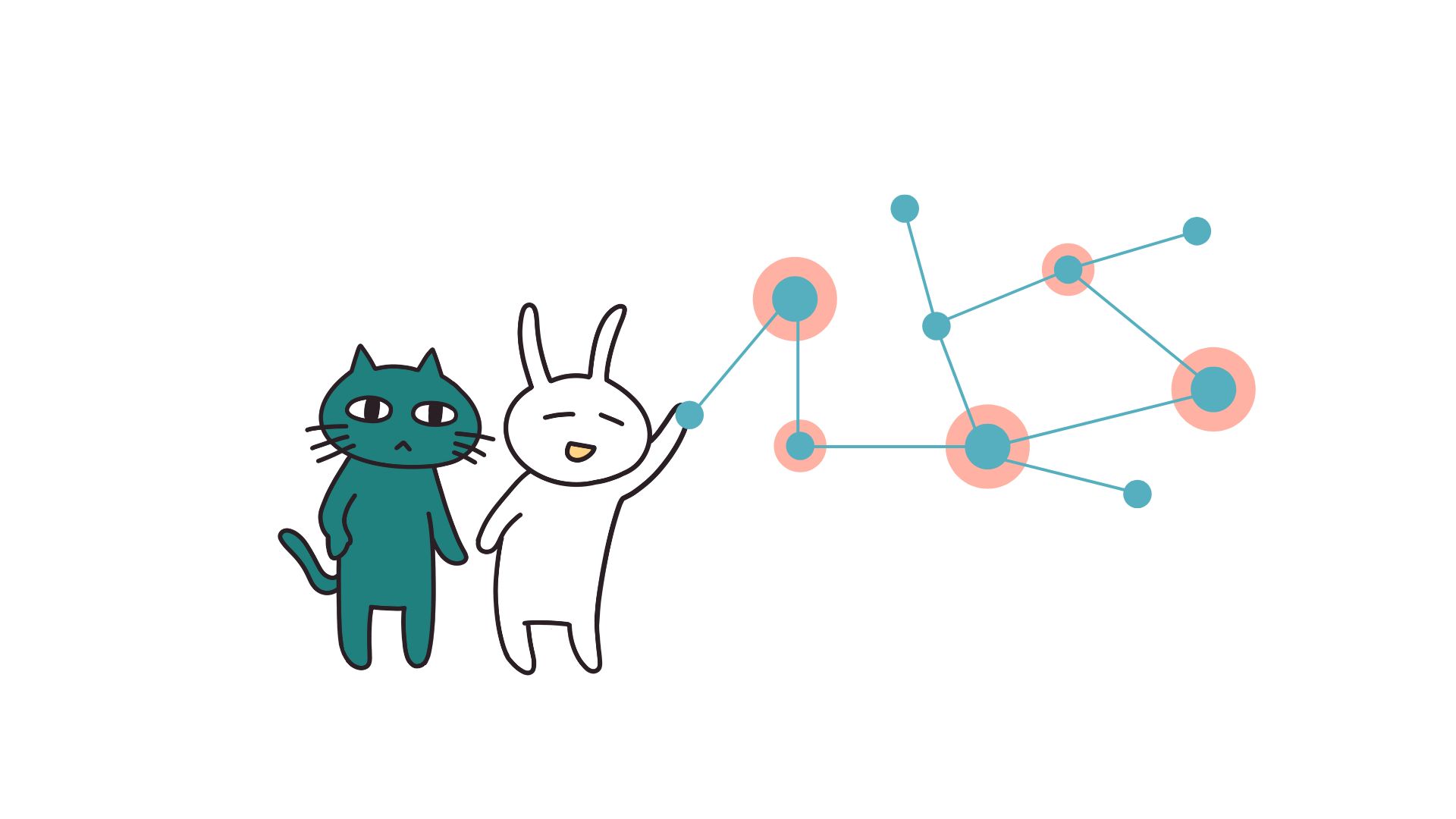
コメントを投稿
別ページに移動します