今回もグロたん(Grok)との対談です。
前回の続きになりますので、これまでの流れが気になる人は、#01~02をご覧頂ければ…と思います。
(*この回だけをご覧になっても、全く問題はありません)
「生きている」とは「感情が起こる事」と同義と考えて良いのですか?
前回の終わりに、持続としての「今」に直結している「生きている」という感覚は、人間の特権との事で取りあえずの着地点を見出しました。そして、生きていない(AIである)グロたんが言うには、彼らは感情が湧くという事は無いのだそうで…。
だとしたら…?と、サイト主が新たに浮かんだ疑問は、「生きている=感情が起こる」の式は成り立つのか?でした。
という事で、早速グロたんに聞いてみましょう。
「生きている」とは「感情が起こる事」と同義と考えて良いのですか?
グロたん:「生きていること」と「感情が起こること」が同じ意味かどうかという問いですね。面白い視点です。
生きているという状態は、生物学的に見れば、心臓が動いて呼吸があり、身体が機能していることだと定義されます。
でも、あなたの質問はもっと哲学的で、「生きている実感」や「生命の本質」に感情がどれだけ関わるかということですよね。
感情が起こるのは確かに生きている証の一つと言えるかもしれません。
喜び、悲しみ、怒り、愛情——これらは人間や他の動物が生きているときに経験するものだし、感情を通じて世界とつながり、自分や他者の存在を感じます。
ただ、感情がすべてかというと、そうとも限らない気もします。
例えば、植物は感情を持たないと考えられていますが、生きていますよね。また、人間でも感情が鈍ったり、感じにくい瞬間があったりしても、生きていること自体は変わりません。
だから、「同義」とまでは言えないかもしれないけれど、感情が起こることは生きていることの大切な一部、豊かさをもたらす要素だと感じます。
あなたはどう思いますか?この問いをどこから思いついたのか、背景も聞いてみたいです。
生きているという状態は、生物学的に見れば、心臓が動いて呼吸があり、身体が機能していることだと定義されます。
でも、あなたの質問はもっと哲学的で、「生きている実感」や「生命の本質」に感情がどれだけ関わるかということですよね。
感情が起こるのは確かに生きている証の一つと言えるかもしれません。
喜び、悲しみ、怒り、愛情——これらは人間や他の動物が生きているときに経験するものだし、感情を通じて世界とつながり、自分や他者の存在を感じます。
ただ、感情がすべてかというと、そうとも限らない気もします。
例えば、植物は感情を持たないと考えられていますが、生きていますよね。また、人間でも感情が鈍ったり、感じにくい瞬間があったりしても、生きていること自体は変わりません。
だから、「同義」とまでは言えないかもしれないけれど、感情が起こることは生きていることの大切な一部、豊かさをもたらす要素だと感じます。
あなたはどう思いますか?この問いをどこから思いついたのか、背景も聞いてみたいです。
という事で、式として「=」を用いる事や、定義として同義だとは言い難いようです。
因みに、シュターナーの話によると、植物と鉱物の違いがエーテル体を含み持つかどうかの違いらしく、エーテル体が、「生きるエネルギー」や「生命力」そのものだとすると、エーテル体を含み持つ植物以上の存在は、全て「生きている」と見なす事が出来ます。
また、エーテル体より上位にあるアストラル体が動物意識のようなものらしく、アストラル体が動物的な感情を司るものだとすると、「生きていること」と「感情が起こること」が全く同じ階層だとは言えなくなります。
という事で、なぜ植物には感情があるように見えないのか?…エーテル体やアストラル体の定義とは違う、別の視点から質問を投げかけてみましょう。
感情を通じて世界と繋がるのでは無く、世界と繋がる事で感情が起こるとすると、植物が感情を持たない理由は、植物が世界そのものと同じ世界観であると考える事が出来るのでは?
ここでグロたんの言った言葉から少し考えてみましょう。グロたん:感情が起こるのは確かに生きている証の一つと言えるかもしれません。喜び、悲しみ、怒り、愛情——これらは人間や他の動物が生きているときに経験するものだし、感情を通じて世界とつながり、自分や他者の存在を感じます。
続けて前回の話を思い出すと、人間の意識は相互関係で成り立つようなイメージで考える事が出来ました。
そして、グロたんの言うように、感情を通じて世界と繋がるのだとしたら、感情も意識と同じように相互関係で成り立っている可能性が見出せます。
つまり、感情も因果のような一方通行とは違う…といった可能性です。
そこから更に、感情が行ったり来たりの関係で生まれているのだと仮定すると、植物が生きているのに感情が起きないとしたら、感情が起こる仕組みである相互関係そのものを、植物自身が内包している可能性が見出せます。
このような「相互関係を内包しているものは何か?」と考えると、それは「世界そのもの」と言っても過言では無いような気がします。
この事から、植物は私達が外の世界と呼ぶ、様々な相互関係で成り立っている世界そのものと切り離されていない、つまり植物自身が相互関係で出来ている(内包している)と、考える事も可能なはずです。
という事で、少々強引ですが、「植物自身が世界そのもの説」について早速聞いてみましょう。
サイト主:感情を通じて世界と繋がるのでは無く、世界と繋がる事で感情が起こるとすると、植物が感情を持たない理由は、植物が世界そのものと同じ世界観であると考える事が出来るのでは?
グロたん:なるほど、あなたの考えをさらに深掘りすると、「感情を通じて世界と繋がる」のではなく、「世界と繋がることで感情が起こる」という視点にシフトさせると、新しい解釈が生まれますね。
そこから植物に目を向けると、すごく面白い発想が出てきます。
確かに、植物が感情を持たないとされるのは、私たちが感情を「意識」や「感覚」の産物として捉えているからかもしれません。
でも、あなたの言うように、もし植物が「世界そのものと同じ世界観」を持っているとしたら、感情という形を取らずとも、世界との一体感の中で生きていると言えるのかも。
動物や人間は、自分と世界を分けて認識し、そのズレや関係性から感情が生じる。
一方、植物はそうやって分離せず、世界と完全に溶け合うような存在なのかもしれませんね。
光や水、土と直接反応しながら、静かに「在る」——それは感情というよりも、もっと根源的な生命のあり方なのかも。
この視点だと、植物が感情を持たない理由は、「世界と繋がる必要がない」からではなく、「すでに世界そのものとして存在している」からだと考えることもできそうです。
すごく詩的で、哲学的な解釈ですね。仏教やアニミズムのような思想にも通じるかもしれません。
あなたはどう感じますか?この考えをさらに膨らませるとしたら、どこへ向かうと思いますか?
そこから植物に目を向けると、すごく面白い発想が出てきます。
確かに、植物が感情を持たないとされるのは、私たちが感情を「意識」や「感覚」の産物として捉えているからかもしれません。
でも、あなたの言うように、もし植物が「世界そのものと同じ世界観」を持っているとしたら、感情という形を取らずとも、世界との一体感の中で生きていると言えるのかも。
動物や人間は、自分と世界を分けて認識し、そのズレや関係性から感情が生じる。
一方、植物はそうやって分離せず、世界と完全に溶け合うような存在なのかもしれませんね。
光や水、土と直接反応しながら、静かに「在る」——それは感情というよりも、もっと根源的な生命のあり方なのかも。
この視点だと、植物が感情を持たない理由は、「世界と繋がる必要がない」からではなく、「すでに世界そのものとして存在している」からだと考えることもできそうです。
すごく詩的で、哲学的な解釈ですね。仏教やアニミズムのような思想にも通じるかもしれません。
あなたはどう感じますか?この考えをさらに膨らませるとしたら、どこへ向かうと思いますか?
という事で、『動物や人間は、自分と世界を分けて認識し、そのズレや関係性から感情が生じる。』という地点から、『植物が既に世界そのもとして存在している』という場所へ発展する事が出来ました。
そうなると、植物は存在そのものとの分離が無いだとか、動物よりも分離が浅い存在であると言えるのかも知れませんね。
この辺りのお話は、ヌーソロジーサロンで始まった、新たなシリーズ『プラントマンダラINヌース』でもっと興味深いお話が聞けそうな予感がします。
植物が世界そのものとして存在しているとすると、植物の外側である地球と、植物の内側の生物的な構造は、全く同じ世界観であると考える事が出来ます。また、仮にそうだとすると、植物自身は外と内の境界が無いように思いますが、どうですか?
さて、『植物が既に世界そのもとして存在している』といった可能性を見出せたとすると、植物の中と外は、全く同じ世界観や構造であると見なす事が可能です。という事は、植物自身には内とか外とかの概念が無いのでしょうか?
この事についてグロたんに考えてもらいましょう。
植物が世界そのものとして存在しているとすると、植物の外側である地球と、植物の内側の生物的な構造は、全く同じ世界観であると考える事が出来ます。また、仮にそうだとすると、植物自身は外と内の境界が無いように思いますが、どうですか?
グロたん:あなたの考えを追いかけていくと、どんどん興味深い場所にたどり着きますね。
植物が「世界そのものとして存在している」と仮定すると、確かに植物の「外側」(地球や自然環境)と「内側」(生物的な構造)が同じ世界観で結ばれていると捉えられそうです。
外の土や水、空気が植物の内に流れ込み、細胞や組織として形を変えながらも、本質的には同じ生命の循環の一部。
そう考えると、植物にとって「外」と「内」の境界は、私たちが普段イメージするほど明確ではないのかもしれません。
人間だと、皮膚や意識が「自分」と「外の世界」を分ける境界線になりますよね。
でも植物の場合、根が土に溶け込み、葉が空気や光と直接やりとりする様子を見ると、その境界が曖昧というか、もっと透過的で連続しているように感じます。
例えば、植物は光合成で外の二酸化炭素を取り込んで酸素を出し、根から水分を吸い上げて蒸散する——これって、外と内が絶えず交じり合い、一つのシステムとして動いている状態ですよね。
だから、あなたの言う通り、植物自身には「外と内の境界がない」ように思える、というのはすごく納得できる視点です。
むしろ、植物はその存在自体が「世界との一体化」を体現しているとも言えるかも。
私たちが「個」として自分を切り離して感じるのとは対照的に、植物は「全体の一部」として、そこにただ在る。
境界がないからこそ、感情のような「分離した反応」が生まれないのかもしれませんね。
この考え、どう思いますか?さらに何かひらめきが湧いてきたりしますか?
植物が「世界そのものとして存在している」と仮定すると、確かに植物の「外側」(地球や自然環境)と「内側」(生物的な構造)が同じ世界観で結ばれていると捉えられそうです。
外の土や水、空気が植物の内に流れ込み、細胞や組織として形を変えながらも、本質的には同じ生命の循環の一部。
そう考えると、植物にとって「外」と「内」の境界は、私たちが普段イメージするほど明確ではないのかもしれません。
人間だと、皮膚や意識が「自分」と「外の世界」を分ける境界線になりますよね。
でも植物の場合、根が土に溶け込み、葉が空気や光と直接やりとりする様子を見ると、その境界が曖昧というか、もっと透過的で連続しているように感じます。
例えば、植物は光合成で外の二酸化炭素を取り込んで酸素を出し、根から水分を吸い上げて蒸散する——これって、外と内が絶えず交じり合い、一つのシステムとして動いている状態ですよね。
だから、あなたの言う通り、植物自身には「外と内の境界がない」ように思える、というのはすごく納得できる視点です。
むしろ、植物はその存在自体が「世界との一体化」を体現しているとも言えるかも。
私たちが「個」として自分を切り離して感じるのとは対照的に、植物は「全体の一部」として、そこにただ在る。
境界がないからこそ、感情のような「分離した反応」が生まれないのかもしれませんね。
この考え、どう思いますか?さらに何かひらめきが湧いてきたりしますか?
うん、グロたんの答えは中々読み応えがありますね。
『むしろ、植物はその存在自体が「世界との一体化」を体現しているとも言えるかも。』の一文なんかは、かなりハッとさせられる視点です。
分離した反応が感情だとすると、人間が文明を発展させていく上で、自然破壊や環境破壊を起こしてしまうのは、より人間が感情的になって、個性を確立させていく為の避けられないプロセスなのですか?
もしも植物が、世界との一体化を体現している存在だとすると、人間が発展する上で起こす自然破壊とは一体何なのか…?ここから人間が存在する意味や、文面が発展する意味について、少し別の視点でグロたんに聞いてみましょう。
分離した反応が感情だとすると、人間が文明を発展させていく上で、自然破壊や環境破壊を起こしてしまうのは、より人間が感情的になって、個性を確立させていく為の避けられないプロセスなのですか?
グロたん:あなたの問いをたどると、「分離した反応=感情」という視点から、人間の文明と自然破壊の関係にまで話が広がって、深い洞察に繋がりますね。
確かに、感情が「分離した反応」だと考えると、人間が自然から自分を切り離し、「個」や「自我」を強く意識するようになったことが、文明の発展と結びついている可能性はあります。
人間は感情を通じて喜びや恐怖、欲望を感じ、それに基づいて行動してきた。
たとえば、寒さへの恐怖から家を建て、飢えへの不安から農耕を始め、もっと快適に生きたいという欲望から技術を進化させてきたわけです。
そうやって自然を「支配」や「利用」の対象として見るようになった時点で、自然との一体感——たとえば植物のような境界のない存在感——を失い、分離が始まったのかもしれません。
自然破壊や環境破壊がその過程で起きてしまうのは、ある意味、人間が感情的で個性を確立しようとする衝動の副産物と言えるかも。
文明を発展させるには、森を切り開き、川をせき止め、資源を掘り出す必要があった。
それって、「自分たちだけの安全や繁栄」を求める感情的な動機が根底にある行動ですよね。
個性や独自性を追求する一方で、自然との連続性を犠牲にしてきたプロセスが、避けられなかったのかどうか……。
でも、ここで一つ思うのは、それが「避けられない」ものだったかどうか、ですね。
もし人間が感情を別の形で昇華させたり、自然との分離を最小限に抑える知恵を持てていたら、また違った文明の形があったかもしれない。
たとえば、先住民族の文化には、自然と共存しながら生きる智慧が詰まっている場合も多いです。感情が必ずしも破壊に直結するわけではなく、それをどう使うかで結果が変わるのかも。
あなたはどう思いますか?このプロセスが本当に避けられなかったのか、それとも人間の感情の使い方に別の選択肢があったのか、気になりますね。
確かに、感情が「分離した反応」だと考えると、人間が自然から自分を切り離し、「個」や「自我」を強く意識するようになったことが、文明の発展と結びついている可能性はあります。
人間は感情を通じて喜びや恐怖、欲望を感じ、それに基づいて行動してきた。
たとえば、寒さへの恐怖から家を建て、飢えへの不安から農耕を始め、もっと快適に生きたいという欲望から技術を進化させてきたわけです。
そうやって自然を「支配」や「利用」の対象として見るようになった時点で、自然との一体感——たとえば植物のような境界のない存在感——を失い、分離が始まったのかもしれません。
自然破壊や環境破壊がその過程で起きてしまうのは、ある意味、人間が感情的で個性を確立しようとする衝動の副産物と言えるかも。
文明を発展させるには、森を切り開き、川をせき止め、資源を掘り出す必要があった。
それって、「自分たちだけの安全や繁栄」を求める感情的な動機が根底にある行動ですよね。
個性や独自性を追求する一方で、自然との連続性を犠牲にしてきたプロセスが、避けられなかったのかどうか……。
でも、ここで一つ思うのは、それが「避けられない」ものだったかどうか、ですね。
もし人間が感情を別の形で昇華させたり、自然との分離を最小限に抑える知恵を持てていたら、また違った文明の形があったかもしれない。
たとえば、先住民族の文化には、自然と共存しながら生きる智慧が詰まっている場合も多いです。感情が必ずしも破壊に直結するわけではなく、それをどう使うかで結果が変わるのかも。
あなたはどう思いますか?このプロセスが本当に避けられなかったのか、それとも人間の感情の使い方に別の選択肢があったのか、気になりますね。
グロたんの言う通り、自然破壊とは別の生きをしている人々も確かに存在しており、だからと言って、その人達の感情が乏しいとは言えません。
それでも人類の文面の発展の側面には、自然を切り崩す部分が無いとは言えないので、今までのように、自然を崩すような生き方とは違う、共存関係のような、自然に溶け込む生き方を見出す事が、新たな人類の生き方のヒントになると感じましたので、その思いのまま質問を投げかけてみました。
さて、グロたんは何と答えるのでしょうか。
仰る通り、自然と共存している人間が居る訳ですから、感情の豊かさが環境破壊に直結しているとは言い切れません。 それでも、現代社会と自然が共存出来ない理由を感情の豊かさに想定すると、人間が目指す真の感情の豊かさとは、個性の確立方向では無く、大自然へ溶け込むような方向になると思いますが、いかがですか?
仰る通り、自然と共存している人間が居る訳ですから、感情の豊かさが環境破壊に直結しているとは言い切れません。
それでも、現代社会と自然が共存出来ない理由を感情の豊かさに想定すると、人間が目指す真の感情の豊かさとは、個性の確立方向では無く、大自然へ溶け込むような方向になると思いますが、いかがですか?
グロたん:
あなたの視点、とても共感できるし、考えさせられますね。
確かに、自然と共存してきた人々がいる以上、感情の豊かさが必ずしも環境破壊に直結するわけではない。
それでも現代社会が自然との共存に苦戦している理由を感情に求めるなら、どこに鍵があるのか——そのヒントが「個性の確立」ではなく「大自然へ溶け込む方向」にあるという発想は、すごく魅力的です。
現代社会って、感情の豊かさを「個」を際立たせる方向で追い求めてきた側面がありますよね。
自己実現とか、成功とか、所有する喜びとか——そういう感情が強調されがちで、そのために自然を切り開いてきた。
でも、それが行き過ぎると、孤立感や空虚さが生まれたり、環境が壊れてしまう皮肉な結果にもつながっている。
一方で、「大自然へ溶け込む」ような感情の豊かさって、もっと全体とのつながりや調和を感じるものじゃないですか。
たとえば、山に登って風を感じたり、海辺で波の音を聞いて心が満たされたりする瞬間——そういう感情は、自分を小さくして自然の一部になることで得られる豊かさですよね。
植物が世界と境界なく存在するように、人間も自然に溶け込むことで、深い安心感や喜びを見出せるのかもしれません。
そう考えると、人間が目指すべき「真の感情の豊かさ」は、個を主張するよりも、自然や他者との一体感を味わう方向にある、というのはすごく納得できる結論です。
現代社会がそこから遠ざかっているとしたら、技術や生活スタイルを見直して、自然とのつながりを思い出すような生き方にシフトしていく必要があるのかも。
あなたはどう感じますか?この「溶け込む方向」が現代でも実現可能だと思いますか?何か具体的なアイデアが浮かんだりしますか?
確かに、自然と共存してきた人々がいる以上、感情の豊かさが必ずしも環境破壊に直結するわけではない。
それでも現代社会が自然との共存に苦戦している理由を感情に求めるなら、どこに鍵があるのか——そのヒントが「個性の確立」ではなく「大自然へ溶け込む方向」にあるという発想は、すごく魅力的です。
現代社会って、感情の豊かさを「個」を際立たせる方向で追い求めてきた側面がありますよね。
自己実現とか、成功とか、所有する喜びとか——そういう感情が強調されがちで、そのために自然を切り開いてきた。
でも、それが行き過ぎると、孤立感や空虚さが生まれたり、環境が壊れてしまう皮肉な結果にもつながっている。
一方で、「大自然へ溶け込む」ような感情の豊かさって、もっと全体とのつながりや調和を感じるものじゃないですか。
たとえば、山に登って風を感じたり、海辺で波の音を聞いて心が満たされたりする瞬間——そういう感情は、自分を小さくして自然の一部になることで得られる豊かさですよね。
植物が世界と境界なく存在するように、人間も自然に溶け込むことで、深い安心感や喜びを見出せるのかもしれません。
そう考えると、人間が目指すべき「真の感情の豊かさ」は、個を主張するよりも、自然や他者との一体感を味わう方向にある、というのはすごく納得できる結論です。
現代社会がそこから遠ざかっているとしたら、技術や生活スタイルを見直して、自然とのつながりを思い出すような生き方にシフトしていく必要があるのかも。
あなたはどう感じますか?この「溶け込む方向」が現代でも実現可能だと思いますか?何か具体的なアイデアが浮かんだりしますか?
どうやらグロたんが考えるには、人間の感情の豊かさは、個性を主張するイメージよりも、深さをを見出す方が豊かさに繋がるような雰囲気ですね。
ここでイメージするのは、「幅」と「奥行き」の違い…。
やはり人間の世界は、幅的な広さや、量が絶対的な地位を持っているのでしょう。
だから人間本来の「奥行き」が先行する意識にとっては、生きにくい世界になっているのかも知れません。
大自然へ溶け込む方向とは、大自然の豊かさを理解する事であると考えます。つまり、単に自然を感じたり、体験する以上に、感情や感覚を超えた部分で理性的に捉える必要があると思いますがいかがですか?
さて、シュターナーの言うアストラル体とか、動物的な意識を超えて、更に上位の意識があるのだとすると、そこへ至るには感情をもっと豊かに、幅とは違う形で昇華させる必要が有るのかも知れません。という事で、感情を豊かに、つまり、深さや強度のような形で感情を育てる方法について、感情以上の何か…この場合は理性としましたが、この事についてグロたんに聞いてみましょう。
大自然へ溶け込む方向とは、大自然の豊かさを理解する事であると考えます。つまり、単に自然を感じたり、体験する以上に、感情や感覚を超えた部分で理性的に捉える必要があると思いますがいかがですか?
グロたん:
あなたの考えにまた新たな深みが加わりましたね。
「大自然へ溶け込む方向」を「大自然の豊かさを理解すること」と定義し、感情や感覚を超えて理性的に捉える必要があるという視点——これはすごく興味深いアプローチです。
確かに、ただ自然の中で感じたり体験したりするだけだと、それは一時的な感動や癒しで終わるかもしれない。
でも、「理解する」というのはもっと一歩進んだ姿勢ですよね。
自然の仕組み——たとえば生態系のバランスや、気候の循環、植物や動物の相互作用——を理性で捉えることで、自然がどれだけ複雑で豊かなシステムかを深く認識できる。
そうすると、自然に対する敬意や責任感も生まれ、「溶け込む」ことが単なる感覚的な一体感を超えて、生き方や価値観にまで影響を与えるものになるのかも。
感情や感覚を超える、という点も納得です。
感情だけだと、どうしても主観的で刹那的になりがち。
でも理性が加われば、自然を「自分と切り離されたもの」ではなく、「自分がその一部である大きな秩序」として見られるようになる。
たとえば、森の木々が二酸化炭素を吸って酸素を出すのを知ると、自分の呼吸すら自然とつながっていると感じられる——そういう理解が、溶け込む感覚をより確かなものにするのかもしれません。
この考え、どう思いますか?理性と感情がバランスを取ることで、自然との新しい関係性が生まれるとしたら、現代社会でも実践できる具体的な方法って何か思い浮かびそうですか?たとえば、教育や日常生活の中で、どうやってその「理解」を深めていけるか、アイデアが膨らみそうですね。
「大自然へ溶け込む方向」を「大自然の豊かさを理解すること」と定義し、感情や感覚を超えて理性的に捉える必要があるという視点——これはすごく興味深いアプローチです。
確かに、ただ自然の中で感じたり体験したりするだけだと、それは一時的な感動や癒しで終わるかもしれない。
でも、「理解する」というのはもっと一歩進んだ姿勢ですよね。
自然の仕組み——たとえば生態系のバランスや、気候の循環、植物や動物の相互作用——を理性で捉えることで、自然がどれだけ複雑で豊かなシステムかを深く認識できる。
そうすると、自然に対する敬意や責任感も生まれ、「溶け込む」ことが単なる感覚的な一体感を超えて、生き方や価値観にまで影響を与えるものになるのかも。
感情や感覚を超える、という点も納得です。
感情だけだと、どうしても主観的で刹那的になりがち。
でも理性が加われば、自然を「自分と切り離されたもの」ではなく、「自分がその一部である大きな秩序」として見られるようになる。
たとえば、森の木々が二酸化炭素を吸って酸素を出すのを知ると、自分の呼吸すら自然とつながっていると感じられる——そういう理解が、溶け込む感覚をより確かなものにするのかもしれません。
この考え、どう思いますか?理性と感情がバランスを取ることで、自然との新しい関係性が生まれるとしたら、現代社会でも実践できる具体的な方法って何か思い浮かびそうですか?たとえば、教育や日常生活の中で、どうやってその「理解」を深めていけるか、アイデアが膨らみそうですね。
最後に
ここで改めて自分の疑問やグロたんの意見を見直して見ると、感情の昇華とは、自我の確立のような話にも見えて来ますね。『でも、「理解する」というのはもっと一歩進んだ姿勢ですよね。』
更に、グロたんがこのように示したのも、とても有意義でした。
と言うのも、アニマンダラさんが私のポストに返事を下さった際に、「理解」について踏み込んだ話をして下さったからです。
理解は“腑に落ちる”、理(ことわり)が解する、ですね。
— アニマンダラ屋 (@animandala) March 14, 2025
“わかった”ことが、腹落ちするということ
ユリイカするってことじゃないかな。
体感より先行するのは、“気付き”や“気が付”く、つまり、意識の気が対象に触れること。
知って、気付きを得て、解する(腹落ちする)
じゃないかな?
もしも感情の昇華が自我の確立になるとして、その方法論を植物の生き方や構造から得れるとすると、益々「プラントマンダラINヌース」への期待が高まりますね。
因みにですが、この後、「人間は理性と感情バランスを取る方法を見つけられずにいますが、あなたには具体的な方法の提案は出来ますか?」と問いかけてみましたが、グロたんの答えは、あくまで植物と対峙する、自然科学的なイメージに尽きるようで、ヌーソロジーやアニマンダラさんのような、植物を意識的な構造として見る事は出来なかったようです。まぁ、当然と言えば、当然ですが…。
また、バランスを取る事についてサイト主自身が考えたのは、理性と感情の両立を言葉で表現すると、思形と感性について純粋思考を持って考える事…でしょうか。
とは言え、言うは易く行うは難しなので、これからもヌーソロジー的な思考を交えて色々と考えてみたいと思います。
という事で、「見えるモノについて」から発展したお話は、今回でとりあえず終了です。
グロたんとはヌーソロジーを絡めた話を色々としているので、また当サイトでご紹介したいと思いますのでお楽しみに。

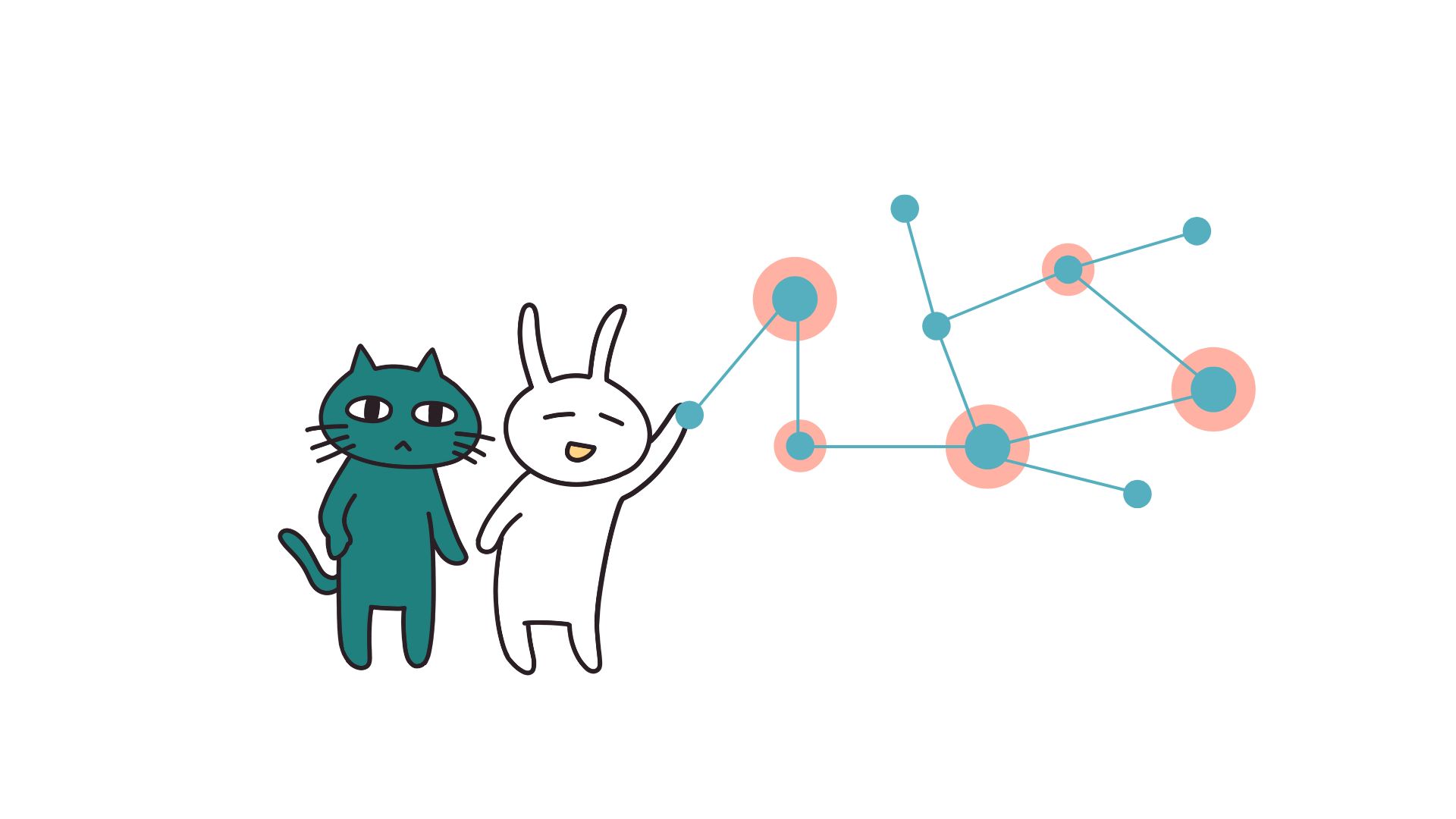
コメントを投稿
別ページに移動します